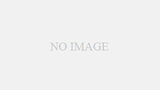最近興味があり学習している行動経済学に関連するワードをまとめます。
バイアス(認知バイアス)
- 確証バイアス(Confirmation Bias)
- 自分の先入観を裏付ける情報ばかり集めてしまう傾向
- 例:SNSで政治のニュースを見るとき、自分の意見に合う情報ばかり読んで反対意見を無視する
- 後知恵バイアス(Hindsight Bias)
- 結果を知った後で「それは予測できたはず」と考えてしまう傾向
- 例:サッカーの試合後、「この戦術なら勝てると思ってた」と後付けで言うが、試合前はそんな発言はしていなかった
- 自信過剰バイアス(Overconfidence Bias)
- 自分の判断や能力を過大評価するバイアス
- 例:投資初心者が「自分は市場を予測できる」と過信し、大胆に資産を投じて大損する
- アンカリング効果(Anchoring Effect)
- 最初に提示された数字や情報に引きずられて判断してしまう現象
- 例:家電量販店で「通常価格10万円が今なら5万円!」と表示されると、本来の価値を考えずお得に感じてしまう
- フレーミング効果(Framing Effect)
- 表現や提示の仕方によって意思決定が変わる現象
- 例:「この手術の成功率は90%」と言われると安心するが、「失敗率10%」と言われると不安になる
- 現状維持バイアス(Status Quo Bias)
- 変化を嫌い、現在の状態を維持しようとする傾向
- 例:通信プランを見直せば安くなると知りながら、手続きが面倒でそのままにする
- 損失回避(Loss Aversion)
- 利得より損失を過大に重く感じ、損失を避けようとする傾向
- 例:1000円を得る喜びより、1000円を失うショックの方が大きく感じる
- エンドウメント効果(Endowment Effect)
- 自分が一度手にしたものに高い価値を感じてしまう傾向
- 例:フリーマーケットで、自分が持っている商品を相場より高く売ろうとする
- サンクコストの誤謬(Sunk Cost Fallacy)
- 埋没費用にとらわれ、損失が出ても投資や行動を続けてしまう誤った判断
- 例:つまらない映画でも「お金を払ったから」と最後まで観てしまう
- ギャンブラーの誤謬(Gambler’s Fallacy)
- 偶然の事象において直前の結果から次の結果を誤って予測する傾向
- 例:「5回連続でコインが表だから、次は裏が出るはず」と誤解する
- セルフサービングバイアス(Self-Serving Bias)
- 成功は自分の手柄、失敗は他の要因のせいにする自己都合のバイアス
- 例:試験に合格したら「努力したから」、不合格なら「試験が難しすぎた」と言う
- 楽観バイアス(Optimism Bias)
- 自分には都合の良い結果が起こりやすいと過度に信じる傾向
- 例:「自分は事故に遭わない」と思い、安全運転を怠る
- ハロー効果(Halo Effect)
- 一つの目立つ特徴が全体の評価に影響し、他の特性まで良いと判断してしまう現象
- 例:イケメンの上司は仕事もできると思い込む
ヒューリスティクス(直感的判断)
- 代表性ヒューリスティック(Representativeness Heuristic)
- 事例が典型的であるほどその確率が高いと判断してしまう直感的ルール
- 例:「Aさんは数学が得意だから、きっとプログラミングもうまいはず」と考える
- 利用可能性ヒューリスティック(Availability Heuristic)
- 思い出しやすい情報や直近の情報を過大評価して判断に使ってしまう直感
- 例:飛行機事故のニュースを見た後、飛行機に乗るのが怖くなる
- 係留と調整ヒューリスティック(Anchoring & Adjustment Heuristic)
- 最初に得た情報(アンカー)を基準にして判断し、不十分な調整しか行わない思考経路
- 例:「1万円で売ります」と言われると、8千円でも安く感じる
- 感情ヒューリスティック(Affect Heuristic)
- 好き嫌いやそのときの感情に基づいて即座に判断してしまう直感的な思考パターン
- 例:友人が勧めたから、その映画は面白いと思い込む
意思決定と選択
- プロスペクト理論(Prospect Theory)
- 人々が損失と利得を評価する際に示す非合理な傾向を説明する理論
- 例:「確実に90万円もらう」のと「90%の確率で100万円、10%の確率でゼロ」では、多くの人が確実な90万円を選ぶ(リスク回避)。一方で、「確実に90万円を失う」のと「90%の確率で100万円を失うが、10%で損失ゼロ」では、多くの人がリスクを取って後者を選ぶ(損失回避)
- 確実性効果(Certainty Effect)
- 確実に得られる選択肢を過大評価し、不確実な選択肢を過小評価する傾向
- 例:「90%の確率で100万円もらえる」と「100%の確率で80万円もらえる」なら、後者を選びやすい
- 選好の逆転(Preference Reversal)
- 提示のされ方や判断方法によって選好が矛盾する現象
- 例:Aプラン(月額5000円無制限)とBプラン(2500円5GB)があるとき最初はBを選ぶが、後で「割引キャンペーンでAプランが1000円引き」と提示されるとAを選ぶようになる
- 後悔回避(Regret Aversion)
- 将来「選択を誤った」と後悔することを恐れ、後悔が少なそうな選択肢を選ぶ傾向
- 例:「高いスマホを買うと後悔しそう」と思い、結局古い機種を使い続ける
- 決定回避(Decision Avoidance)
- 難しい選択や不確実な選択を先延ばししたり回避したりしがちな傾向
- 例:選択肢が多すぎて迷い、何も買わない
- 限定合理性(Bounded Rationality)
- 人間は計算能力や情報に限界があるため、完全には合理的な意思決定ができないという概念
- 例:ネットで家電を購入するとき、すべての選択肢を比較するのは難しいので、レビューの評価が高いものをなんとなく選ぶ
- デコイ効果(Decoy Effect)
- おとりとなる選択肢を加えることで、特定の選択肢の魅力が相対的に高まる現象
- 例:映画館のポップコーンがS:300円、M:600円、L:650円ならLを選びやすい
- 選択肢過多(Paradox of Choice)
- 選択肢が多すぎると意思決定がかえって難しくなり、満足度が下がる傾向
- 例:10種類の服があると選びにくく、買わずに帰る
ゲーム理論と戦略
- 囚人のジレンマ
- 個人の合理的選択が全体として非合理な結果を招くジレンマの代表例となるゲーム
- 例:価格競争で、両社が値下げして共倒れする
- 最後通牒ゲーム(Ultimatum Game)
- 提案者と応答者に分かれた交渉ゲーム
- 不公平な提案はたとえ損しても拒否されることが多く、公平性の偏好を示す実験
- 例:Aさんが1万円を受け取り、それをBさんと分けるよう指示される。Aさんは「7000円は自分、3000円をBさんに分ける」と提案した。しかしBさんは「不公平だ」と感じ、提案を拒否。結果として、AさんもBさんもお金を受け取れなくなる
- 独裁者ゲーム(Dictator Game)
- 一方的な分配ゲーム
- 提案者が任意に配分を決めることで、利他主義や公平性志向の程度を測定する実験
- 例:5000円を持っているプレイヤーが、一方的に3000円を自分に、2000円を相手に分配するよう決められる
- 信頼ゲーム(Trust Game)
- 最初のプレイヤーが金額を送り、受け取ったプレイヤーがそれを増やして返すか決めるゲーム
- 信用と互恵(返報性)の行動を分析する
- 例:友人にお金を貸すと、返してくれるかどうか信頼に関わる
- ナッシュ均衡(Nash Equilibrium)
- 各プレイヤーが自分の戦略を最適に選択しているため、これ以上誰も戦略を変えるインセンティブがない状態
- 例:サッカーのPK戦でキッカーとゴールキーパーがどちらに蹴るか・飛ぶかを決めるとき、それぞれが相手の行動を考慮して戦略を選ぶことで、どちらも変えない均衡が生じる
- しっぺ返し戦略(Tit-for-Tat Strategy)
- 繰り返しゲームにおける戦略の一つ
- 最初は協調し、以降は相手の前回の行動をそのまま返すことで協調と報復のバランスを取る
- 例:ある企業とそのライバル企業は最初は互いに通常価格で販売していたが、一方が値下げするともう一方も対抗して値下げした。その後、元の企業が再び値上げするとライバル企業も同じように値上げし、価格競争が収束した
ナッジと政策応用
- ナッジ(Nudge)
- 人々の行動選択を自由に保ったまま、望ましい方向へそっと後押しする介入
- 例:野菜を目立つ棚に置くと、健康的な食事を選びやすくなる
- リバタリアン・パターナリズム(Libertarian Paternalism)
- 選択の自由を尊重しつつ、人々にとってより良い結果をもたらすように介入する政策哲学
- 選択の自由を尊重しつつ、人々にとってより良い結果をもたらすように介入する政策哲学
- 選択アーキテクチャ(Choice Architecture)
- 意思決定に影響を与えるような選択肢の提示方法や環境の設計
- 意思決定に影響を与えるような選択肢の提示方法や環境の設計
- デフォルト効果(Default Effect)
- あらかじめ設定された選択肢を人々がそのまま受け入れやすい傾向
- 例:会社の年金プランが自動加入だと、多くの人が変更せずにそのまま加入する
市場と行動経済学
- 行動ファイナンス(Behavioral Finance)
- 投資家の非合理な行動や心理バイアスが市場に与える影響を研究する分野
- 投資家の非合理な行動や心理バイアスが市場に与える影響を研究する分野
- バブル(Bubble)
- 資産価格が実体価値から大きくかけ離れて急騰し、その後暴落する現象
- 例:仮想通貨が急騰し、多くの人が買い、最終的に暴落する
- 羊群行動(Herd Behavior)
- 他人の行動につられて多数に追随するような集団的行動
- 例:人気のカフェに行列ができると、自分も並びたくなる
- バンドワゴン効果(Bandwagon Effect)
- 流行や多数派に乗る形で商品の需要や支持が高まる現象
- 例:流行りのスニーカーを皆が履いているので、自分も欲しくなる
- スノッブ効果(Snob Effect)
- 他人と違うものを好む心理により、希少な商品や高級品に需要が集まる現象
- 例:限定品のスニーカーが高値でも売れる
- ヴェブレン効果(Veblen Effect)
- 価格が高いほど需要が高まる現象
- 高価格自体がステータスとなり需要を喚起する
- 例:高級ワインは価格が上がるとむしろ良いものとみなされ、需要が増える
- メンタル・アカウンティング(Mental Accounting)
- お金に対して心の中で異なる勘定を作り、元金の出所や用途によって支出・投資判断が変わる現象
- 例:ボーナスで得たお金はご褒美と考え、普段なら買わない高級ブランド品を買ってしまう
- ディスポジション効果(Disposition Effect)
- 投資家が利益が出ている株は早めに売却し、損失が出ている株は損切りせず保有を続けてしまう傾向
感情と行動
- 認知的不協和(Cognitive Dissonance)
- 自分の中の矛盾する信念や行動に伴う不快感
- それを低減するために合理化したり判断を歪めたりする心理傾向
- 例:「環境に優しい」と言いながら車に乗り続ける人が「電気自動車は高い」と正当化する
- ピーク・エンドの法則(Peak-End Rule)
- 経験の良し悪しの評価は、その最も強いピーク時と終了時の印象によって決まるという法則
- 例:旅行の最後が楽しいと、全体の印象が良くなる
- ヘドニック・アダプテーション(Hedonic Adaptation)
- 嬉しい出来事や悲しい出来事にも人は徐々に慣れてしまい、元の幸福水準に戻ってしまう傾向
- 例:新車を買っても、すぐに慣れて感動が薄れる
- 情動的意思決定
- 怒り・恐怖・喜びなど強い感情状態が判断に影響し、冷静な状態とは異なる選択を引き起こす現象
- 例:ある人が怒っているときに、冷静なら避けられるはずの「言い争い」に突発的に応じてしまい、後で後悔する
- ソマティック・マーカー仮説(Somatic Marker Hypothesis)
- 感情に伴う身体反応が将来の結果を予測するマーカーとなり、意思決定を導くという仮説
- 例:ある人が過去に株で大きな損失を出した経験がある。そのため再びリスクの高い投資をしようと考えたとき、心拍が速くなったり胃がキリキリするような感覚が生じ、「やめておこう」と判断する
時間選好と未来の判断
- 現在志向バイアス(Present Bias)
- 将来より目先の利益や快楽を優先してしまう傾向
- 例:「ダイエットする」と言いながら今日だけケーキを食べる
- 双曲割引(Hyperbolic Discounting)
- 将来の価値を現在から見て過大に割り引いてしまう現象
- 時間が近づくと急にその価値が大きく感じられる
- 例:「今すぐ1万円をもらう」のと「1年後に1万1000円をもらう」かでは、ほとんどの人は「今すぐ1万円」を選ぶ。しかし、「5年後に1万円」か「6年後に1万1000円」の選択では、6年後の1万1000円を選ぶ人が増える
- 時間的不整合性(Time Inconsistency)
- 時間が経つにつれて当初の計画や方針が守れなくなること
- 長期的計画より目前の欲求を優先してしまい、意思決定が非一貫的になる傾向
- 例:年始に「毎日ジムに行く」と決めたが、数週間後にはサボってしまう
- 自己制御問題(Self-Control Problem)
- 将来の目標より目前の誘惑に負けてしまう問題
- 貯蓄やダイエットなどで計画通りに行動できない原因となる
- 例:毎月貯金すると決めても、つい衝動買いしてしまう
- コミットメント装置(Commitment Device)
- 将来の自分が誘惑に負けないよう、あらかじめ行動を縛る仕組み
- 例:貯金を確実にするために、給料が入ったら自動的に貯金口座に一定額が振り込まれる設定をする